島嶼(とうしょ)
- 意味:島、島々
- 豆知識:「島」は「大きなしま」、「嶼」は「小さなしま」という意味を持ちます。
子どものころ、海が好きだった父に連れられて
いくつかの島に泊りがけで遊びに行きました。
海がきれいで、砂浜に桜貝がたくさん落ちていた島を
翌年も訪れたとき、桜貝がぐっと減っているのに気づき
子ども心に「環境破壊」というものを感じました。
泣いた
本を買うと、それだけでたいへんテンションが上がります。
本は、読んでみないことにはおもしろいのか、そうでないのか
そして、好みなのかどうかもわかりません。
作者の方には申し訳ない言い方ですが
当たりなのか外れなのか、読了までわからないわけです。
そういう不確かなものに2千円近くを払うって、
ビビりな私にとってバクチに近い感覚です。
だからこそなのか、とにかく本が好きだからなのか
私にとって、いちばんテンションが上がる買い物は新刊本です。
この記事→「苦行の裁縫、もたつくペイペイ払い」で
「汝、星のごとく」を買ったことを書きましたが
翌日、一気読みしたところ、大当たりでした。
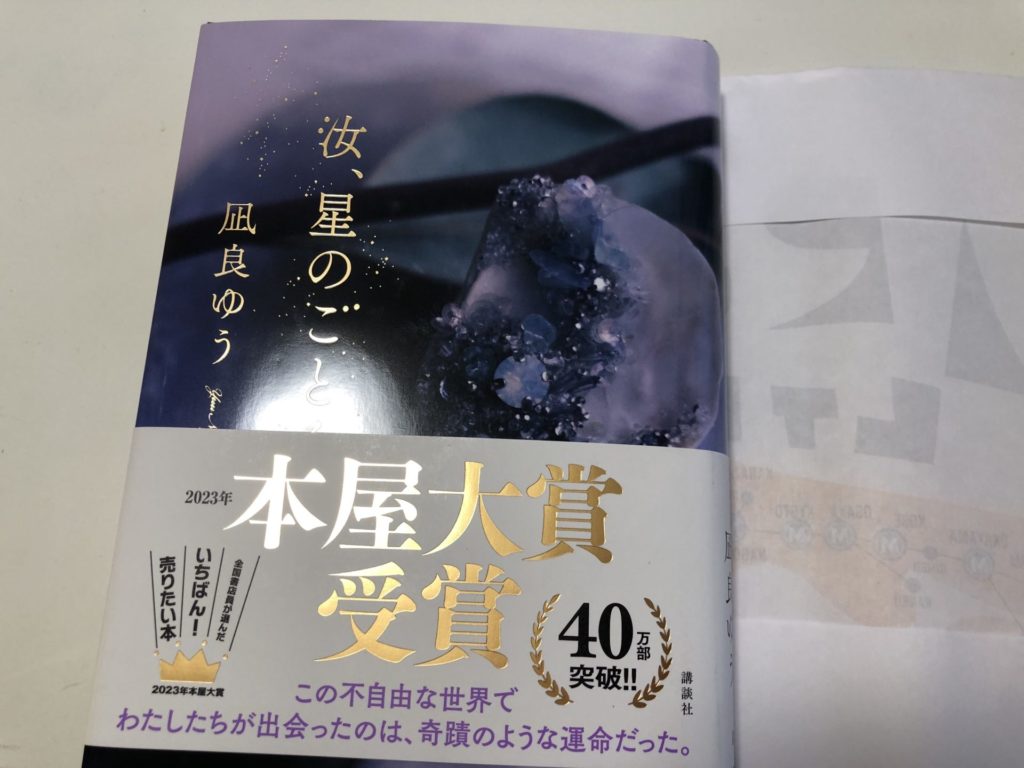
瀬戸内の島に住む男女が主人公で
ふたりが17歳から30代までの物語ですが
全編とおして、息詰まるような閉塞感があり
これは、しんどい人生だなあと、思うのですが
読むのがつらくならないのは、作者の力量なんでしょうね。
読みながら、何度も目に涙がにじみました。
切ないし、やりきれないし、
でも、そうしか生きられないなら仕方ないよねと思うしかないし。
物語の世界の中に、どっぷりと入れる本でした。
買ってよかったと、思えてほっとしています。
やはり高校時代から始まる本
図書館で借りた本「輝跡(柴田よしきさん著)」が、やはり
主人公が高校生から始まり、30代で終わる物語でした。
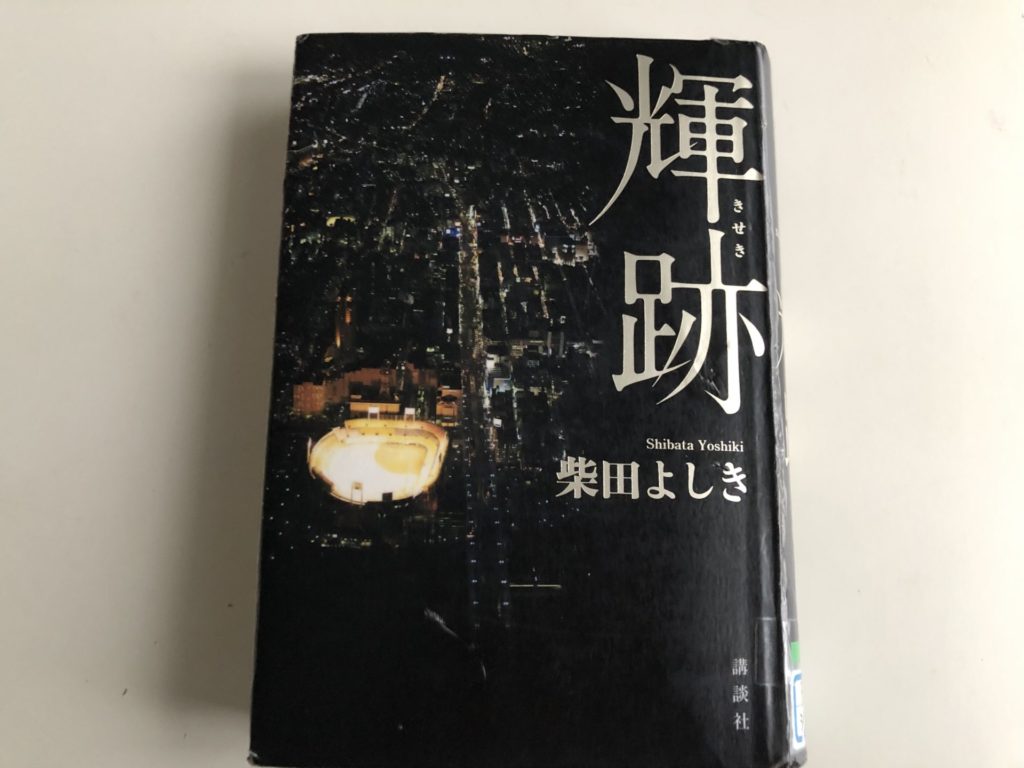
高校生だった男性が、プロ野球選手になり
人気選手になり、ケガをして・・・というストーリーを軸に
その男性にかかわった女性の話がメインの連作短編集です。
「汝、星のごとく」もそうなんですが
物語の中に、登場人物の人生が描かれていて
どうしてこうなるんだ!というもどかしさや
なぜ、ここでそっちを選んじゃうかなあと、いう切なさ
そういうものが感じ取れる話で
好きなジャンルの小説でした。
娘時代
こちらの「草の花(三田完さん著)」も図書館の本で、
やはり、登場人物が10代~30代になるまでの物語でした。

以前記事にした「俳風三麗花」の続編です。
(その記事はこちらです。→イモリなのかヤモリなのかガラかめなのか)
句会で知り合った3人の女性の物語です。
前作では娘時代を過ごしていた3人でしたが
それぞれ、大人の女性となって、時代は戦争に突き進みます。
満州を舞台に、溥儀陛下の御前で開かれた句会があったり
川島芳子や石原莞爾が登場したり
近代史小説としても楽しめるのですが
大人になるということは、なんとも不自由なことか
と、感じるのは現代と同じです。
人として成熟するということは、忍耐を学ぶということで、
若いころ、苦しく感じたことなんて、
振り返れば、何がつらかったのかさえ思い出せないようなことだったよねえと
しみじみと感じたのでした。
家族の物語
ついでにもう1冊、おもしろかった図書館本「始まりの家(蓮見恭子さん著)」です。
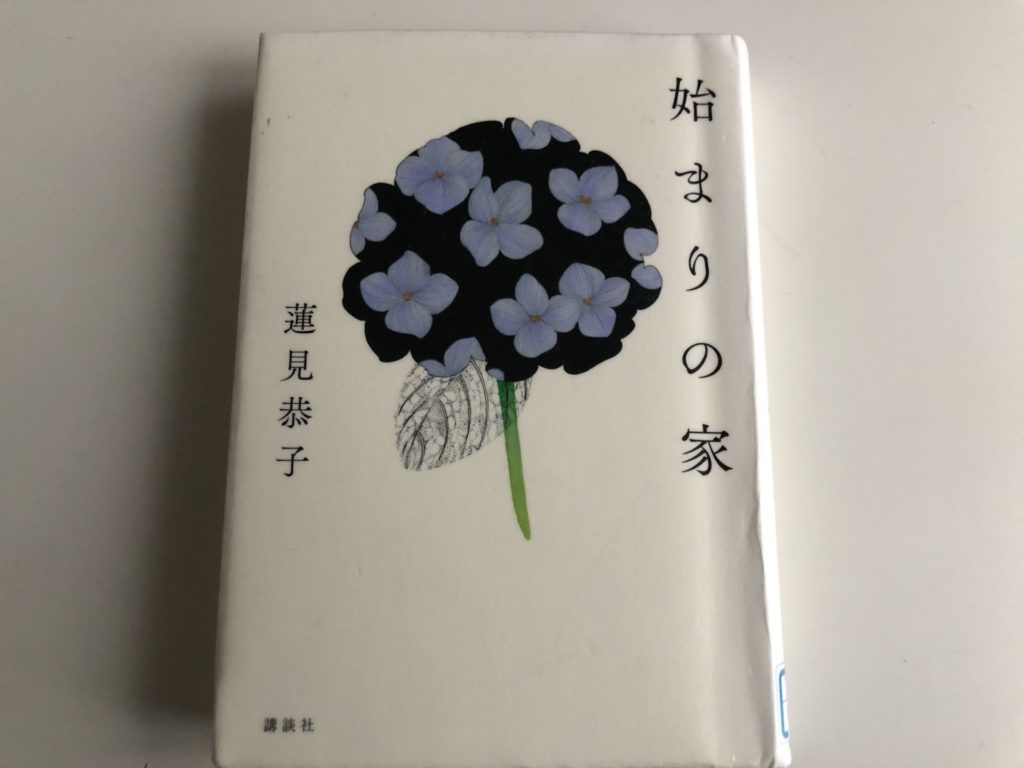
「草の花」の作者、三田完さんも最近読み始めた作家さんですが
こちらの蓮見恭子さんは、この作品が初めて読んだ著作です。
ホステスさん相手の美容院を営む一家の物語で
家族ひとりずつが主人公となる連作短編集なのですが
家族外の登場人物が少しずつ存在感を増していき
あ、この人の人生がこうして重なってくるんだ!
という、おもしろい仕掛けのある小説でした。
本を買うのはバクチのようなものだと、冒頭に書きましたが
図書館は、本がただで借りられるので
タイトル借りや、表紙借りなど
なんとなくおもしろそう?程度の気持ちで手に取ってみます。
そういう借り方で、面白く好みにあう本に出会えると
うれしくもあり、その後その作者の本をもっと読もう!
という楽しみもでき、何倍もお得に感じ、非常に満足します。
この作者さんの著作で、しばらく楽しめそうな予感がしています。
現実から、大きく乖離していないけれど
自分とは、かけ離れた世界、
興味が持てる人生が紡がれている物語が、好きです。
のぞき見趣味的な嗜好ですが、
もっともっとたくさん、そういうおもしろい本に、出会いたいなー。